仮渡金 ついに輸入米レベルに米価に異常あり!自主米の実勢価格は30年前の水準
また、農協が米生産農家に支払う今年産米の仮渡価格は空前の安値で、中には一等米で一俵(六十キロ)八千円(奈良キヌヒカリ)、八千三百円(埼玉あきたこまち)などなど、三十キロ袋の価格かと思わせる水準も。 この結果、たとえば「きらら」の場合、稲得(稲作所得基盤確保対策)の補てん(七百円)を含めても仮渡価格は一万円で、これが最終精算価格になるとすれば、十二年前の半値以下。また、自主流通米価格全体はピークの六割、三十年前(一九七四年)の生産者米価と同じです。
外米価格以下の異常事態とりわけ問題なのは、仮渡価格の水準が外米の輸入原価以下の銘柄が続出していることです。中国米の輸入原価は二〇〇〇年以来、毎年ほぼ千円ずつ上がってきましたが、国産米価格は、昨年の不作による一時的な高騰を除いて、ほぼ一貫して下がり続け、ついに輸入米と肩をならべる水準にまで暴落しています(図1、2)。また、一部の銘柄の三等米価格は六千三百円と、輸入原価の三分の二以下のものさえあります。 しかし、それにしても年収二〜三万円が一般的な中国農民が作る米の価格と日本の農民が作る米の価格が肩をならべるというのは、きわめて異常です。
減反を強制し、何の対策もないまま裸の競争が「米改革」の検討過程で、農水省は、減反を撤廃した場合、米価が八千円まで下がり、その後少し回復して一万二千円で落ち着くという試算を公表したことがあります。また、八月十日に公表された「中間論点整理」は、米の関税がゼロになることも想定して輸入米との裸の競争を強いるとともに、「プロ農家」に限定して、輸入原価と国産米価格との差額を「直接支払い」を行う構想を打ち出しています。 しかし、今年の米価や仮渡金の水準をみれば、これが単なる「試算」や「構想」ではなく、米を輸入しながらの減反を強制したまま、しかも対策は何も講じないまま、輸入米との裸の競争が現実に突きつけられているといわざるをえません。
これが「市場原理」なのか?農民連がこれまで繰り返し指摘してきたように、現在の米価暴落の最大の元凶は、不作に便乗して超古米を放出し続けている政府の「米ビジネス」です。二〇〇二年度末に二百一万トンあった政府在庫は現在、七割減の六十万トン。一方、流通段階には適正在庫の二倍以上の米があふれ、出来秋になっても「米を仕入れできない」事態。これが暴落の引き金です。お盆直前の八月十一日、農民連は政府に“悪徳商法”をやめるよう要請しましたが、返ってきたのは「市場原理で落ち着くべき米価に落ち着いている」という耳を疑うような返事。 第一に、どんな商品にも「生産コスト」があり、市場価格がこれを大幅に下回れば、再生産は保証されません。(図3)のように、自主流通米の全銘柄平均価格に近い千葉県産コシヒカリの実勢価格は一万三千三百円で、通常の生産コストを四千円下回っています。農家は米一俵に千円札を四枚はりつけて出荷しているようなものです。
こういう「市場の暴走」を規制し、米の「需給および価格を安定」(食糧法第一条)させることこそ政府の義務のはずです。 第二に、五百ミリペットボトル一本の水は百五十円ですが、同量の米は、九十〜百円です(米価が一万七千円で)。 また、一戸当たりの経営面積が四千ヘクタール(日本の二千七百倍!)のオーストラリアの農民が作った「有機米」の小売価格が十キロ七千八百円(六十キロ四万六千八百円)と報じられています(日本農業新聞九月九日)。中国でもこの一年間に米の値段が五〜七割上昇しています。 東南アジアや中国では水は一本二十〜三十円ですが、政府は、水は百五十円のまま、米だけは二十〜三十円にしようとでもいうのでしょうか? 賃金・物価事情からすれば、すでに国際的にみても十分に安く、「水」よりも安い「米」をさらに安くする――これが「市場原理」でしょうか!
異常事態の打開は政府の責任私たちは、政府が次の緊急対策をとり、食糧法上の「義務」を果たすことを要求します。(1)「炊飯添加剤」を入れなければ食べられないような七〜八年前の超古米の放出をやめるとともに、加工・飼料用に「区分」保管すること。 (2)米が市場にダブついているときにこそ政府が買い入れて「市場の暴走」をおさえること。そのために、昨年産・今年産を問わず、最低でも百万トン、必要であれば百五十万トンの備蓄水準に達するまで緊急に米を買い入れること。 (3)初年度から破たんが明白な「米改革」をいったん棚上げして見直すこと。とくに発動されれば米価暴落にますます拍車をかけることが明らかな「過剰米処理対策」(集荷円滑化対策)を中止すること。
(新聞「農民」2004.9.27付)
|
[2004年9月]
農民運動全国連合会(略称:農民連)
本サイト掲載の記事、写真等の無断転載を禁じます。
〒173-0025
東京都板橋区熊野町47-11
社医研センター2階
TEL (03)5966-2224
Copyright(c)1998-2004, 農民運動全国連合会
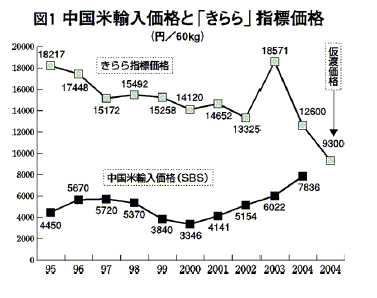 出来秋だというのに、米価が大暴落を続けています。八月二十七日と九月十一日に行われた米価格センターの入札では、どの銘柄も一九九〇年に自主流通米入札が始まって以来の最安値。それでも買い手がつかず、それぞれ六一%、六五%が売れ残るという異常事態。
出来秋だというのに、米価が大暴落を続けています。八月二十七日と九月十一日に行われた米価格センターの入札では、どの銘柄も一九九〇年に自主流通米入札が始まって以来の最安値。それでも買い手がつかず、それぞれ六一%、六五%が売れ残るという異常事態。
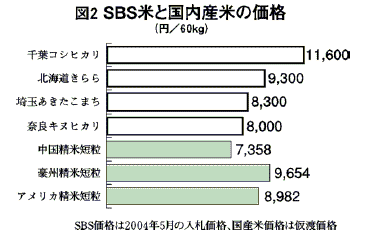 中国米の生産コストは一俵千円前後(二〇〇一年九月、黒竜江省での聞き取り)。また、ジャポニカ米の中国国内での小売価格は一キロ四十八円で、一俵に換算すると二千八百八十円(日本農業新聞九月十六日)。船賃がかかるとしても、途中で商社などが暴利をむさぼっていると推測されます。
中国米の生産コストは一俵千円前後(二〇〇一年九月、黒竜江省での聞き取り)。また、ジャポニカ米の中国国内での小売価格は一キロ四十八円で、一俵に換算すると二千八百八十円(日本農業新聞九月十六日)。船賃がかかるとしても、途中で商社などが暴利をむさぼっていると推測されます。
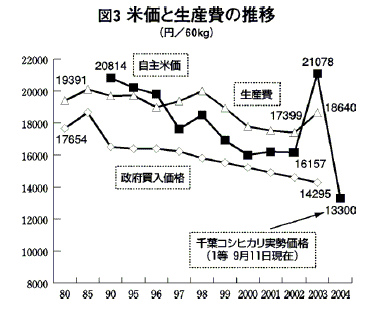 しかし、国産の新米が、大多数の日本人が食べたくないと思っている外米の価格とほぼ同水準という事態は、「市場原理」でも、「落ち着くところに落ち着いている」というものでもありません。
しかし、国産の新米が、大多数の日本人が食べたくないと思っている外米の価格とほぼ同水準という事態は、「市場原理」でも、「落ち着くところに落ち着いている」というものでもありません。