蜂群崩壊症候群に学ぶ
養蜂振興の基盤整備
玉川大学ミツバチ科学研究センター
中村 純 教授の講演
農薬散布などで環境が悪化
エサ資源の増加が大事
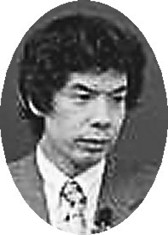 (社)国際農林業協働協会(JAICAP)の主催による講演会が10月7日、農水省内で開かれ、玉川大学ミツバチ科学研究センターの中村純教授が、「蜂群崩壊症候群に学ぶ養蜂(ようほう)振興の基盤整備」と題して講演しました。その一部を紹介します。 (社)国際農林業協働協会(JAICAP)の主催による講演会が10月7日、農水省内で開かれ、玉川大学ミツバチ科学研究センターの中村純教授が、「蜂群崩壊症候群に学ぶ養蜂(ようほう)振興の基盤整備」と題して講演しました。その一部を紹介します。
◇
2006年の冬から翌年の春にかけて、アメリカでミツバチの失そう現象が発生しました。これが蜂群崩壊症候群(CCD)と呼ばれるものですが、いまもって原因は不明で、現象は今も続いています。
現在、ミツバチに異変が起きている地域では、ミツバチは生産性を高めるために工場と化した農地に置かれ、養蜂のイメージである「健康」とはやや隔たった状況にあります。ミツバチは本来、花から花粉と花みつを集めてエサとして生きる生物です。年間を通じて、多様な植物を利用しながら、結果として農業にも貢献してきました。
ところが、自然のエサ資源が開発によって消滅し、農業でのミツバチ利用によってミツバチは主に農地での生態系に移行していると言われています。しかしその農地は、農薬散布などでエサ資源環境が悪化し、ミツバチの基礎体力の低下につながっているのではないか、と言われています。
養蜂の基盤を整備するという観点から見ると、ミツバチが効率重視の農業生産サイクルにほうり込まれたところでは、その基盤が危ういものになっています。ミツバチの基礎体力を回復させるには、農薬の使用をやめることなどを唱えるのではなく、エサとなる資源をどう増やしていくかが大事です。いま、ミツバチの視点で環境を見直すことは、私たち自身の環境を別の角度から見直すよい機会を得たといえます。
直面している問題は大きいが、いたずらに騒ぐのではなく、そこから学ぶことができてこそ、私たちが人間であることの意味があるのです。
(新聞「農民」2009.10.26付)
|