地域を結びまちおこしに貢献
幻の津久井在来大豆
神奈川
10月に名古屋市で生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)が開かれ、在来作物・種子の保存も重要なテーマになります。神奈川県の「津久井在来大豆」は、古くから津久井地域(現相模原市緑区の一部)で農家が自家の加工用として細々と栽培してきた「幻の大豆」です。今では地域振興に大きく貢献し、食と農の大切さを教えています。
(勝又真史)
大豆の自給率上げ全県に大きく広がってほしい
肥料・土作りにこだわって栽培
 「今年は豆のつき方もいい。豊作になりそうです」。相模原市緑区の養鶏農家、石井好一さん(61)は、大きくなり始めた大豆の房を手にしながら満足げに話します。 「今年は豆のつき方もいい。豊作になりそうです」。相模原市緑区の養鶏農家、石井好一さん(61)は、大きくなり始めた大豆の房を手にしながら満足げに話します。
10年前に「何か地域おこしをしようか」と軽い気持ちで始めた津久井在来大豆は今では2ヘクタールに広がりました。農業体験を行っている40人ほどの市民に手伝ってもらいながら栽培しています。また休耕地を活用して受けられる補助金も利用して、30アールほどの休耕地でも作付けしています。
津久井在来大豆は、糖分が高く甘みがあり、加工用に向いています。地元加工業者の力も借りて、みそ、豆腐、納豆などとして製品化されています。石井さんは「大豆から生まれる効果は計り知れない。全県に広がってほしい」と期待を寄せます。
緑区に隣接する愛川町では、神奈川農民連前会長の諏訪部明さん(87)が、市民・消費者でつくる「安全な食を考える会」として一昨年から10アールほど栽培しています。特徴は肥料や土づくりにこだわる「有機栽培」。落ち葉やせん定チップを使ったたい肥は窒素が少なく、育った大豆は、特有の甘みが生きてきます。
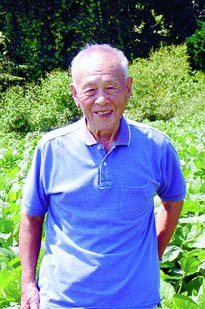 |
|
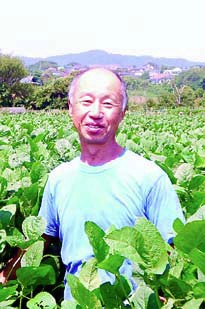 |
諏訪部明さん |
|
石井好一さん |
諏訪部さんは「大豆の自給率が5%と低いなかで、国産大豆を広げるいい機会になってくれれば」と意気込みます。
休耕地活用し作付け
加工に向き商品製造
市内の学校給食に採用
食べやすく栄養素とれる食品に
藤沢市を拠点にして活動する「さがみ地粉の会」(田代幸久会長)。津久井在来大豆は、麦の裏作として始まりました。地元の加工業者と提携し、麦はパンやめん、大豆は豆腐として利用されています。
「地粉の会」に技術指導や情報提供を行うJAさがみ組織経済部顧問の山村高治さん(74)の尽力により、津久井在来大豆が市内の学校給食に採用されることになりました。月1回の「地元産の日」にスープに入った煮豆として登場することもあります。小学生を畑に招き、麦踏みや麦刈り体験を実施して食育にも貢献しています。
石井さん、諏訪部さん、山村さんの共通の願いは「休耕地を活用し、津久井在来大豆を栽培する農家がもっと増えてほしい」ということです。
神奈川県立相原高校(相模原市緑区)食品化学班のみなさんは、学校敷地内の農場で、津久井大豆を栽培、収穫しています。同校では近隣の小学校と連携した食育活動を実施するほか、加工業者の力を借りて、大豆を使った商品開発に力を入れています。
「子どもたちが食べやすく、栄養素がとれる食品はないだろうか」と考えられたのが、きな粉で作った「カムアップ・クッキー」です。津久井在来大豆のきな粉を100%使用し、カルシウムとたんぱく質が豊富で、滑らかな舌触りになるよう豆乳も入れました。
 |
| 「津久井在来大豆で夢、広がれ!」。相原高校食品化学班のみなさん |
苦労のカゲには充実感もあって
部長の宮崎茜さん(3年)は「夏の草むしりはたいへんですが、収穫は大きな喜びです。クッキーを通じて、津久井在来大豆のことを多くの人に知ってもらいたい」、平野未幸さん(3年)は「おいしさと栄養を両方兼ね備えるのは難しい。でも苦労があればそれだけ充実感があります」と語ります。
顧問の田中茂樹先生は「商品開発は、農家と地元企業、学校が連携してできた成果です。津久井在来大豆を通して地域への興味・関心をもってくれれば」と期待を寄せています。
(新聞「農民」2010.9.20付)
|