トランプ関税交渉 米につづいて… トウモロコシ、大豆、ジャガイモも輸入拡大!?(2025年05月19日 第1650号)
農家から怒りと不安の声

5月1日にワシントンで行われた日米関税協議。右から赤沢大臣、ベッセント米財務長官(首相官邸ホームページから)
日米両政府は、アメリカ・トランプ政権による関税措置撤廃に向けた閣僚協議を続けています。アメリカは、米に加えて、他の農畜産物の輸入を迫っています。日本側代表の赤沢亮正経済再生大臣は、トウモロコシや大豆の輸入拡大案などを米国側に提示したと各紙が報道しています。トウモロコシは家畜の飼料用や、自動車・航空機燃料向けバイオエタノール(バイオ燃料)用としての輸入を想定しています。さらに、アメリカ側は、ジャガイモなどの品目を挙げ、輸入拡大を迫っています。日本の農畜産物はどうなるのか。農家の不安と怒りの声を紹介します。
生ジャガイモ輸入拡大で病害虫のまん延が不安

キタアカリ
北海道の畑作農家 大沢稔さん(小清水町)
大豆、ジャガイモなどを栽培しています。アメリカでは、大豆はほとんどが遺伝子組み換えです。遺伝子組み換え大豆が今まで以上に輸入されれば、大豆の自給率が下がるだけでなく、食の安全上も心配です。農家にとっても消費者にとっても大問題です。
アメリカ産ジャガイモは現在、日本への輸出がポテトチップスなど加工用に限定されています。その理由の一つがジャガイモシストセンチュウという病害虫の発生にあります。ジャガイモシストセンチュウは、土の中でジャガイモの根から養分を吸収して、収穫量を大幅に減らしてしまう害虫です。
加工用で輸入する分には、海岸沿いの工場に限定されるなどの規制があり、病害虫のリスクを減らせますが、アメリカは生のままのジャガイモを輸入してくれと要求しているという報道もあります。生のまま輸入するとセンチュウが潜んでいる場合があり、それを種イモに使うとあっという間に日本中に広がるおそれがあります。
政府は、日本の農業を守る気が本当にあるのか。アメリカには毅然とした態度をとってほしい。
輸入飼料への依存進む国産飼料の努力に冷水
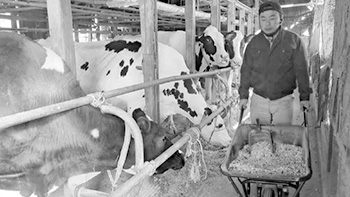
牛に給餌する金谷さん
千葉県の酪農家 金谷雅史さん(千葉市)
酪農危機とうたわれ早3年が経過したが、その間、絶えず言われてきたのは「飼料生産基盤に立脚した酪農」であった。令和7年度予算にも同名の補助金が盛り込まれ、向こう5年間の酪農と肉用牛政策の基本方針でも同様に言及されている。
過度な輸入飼料依存からの脱却が必要なことが明らかな中で、どうやって輸入トウモロコシの消費量を拡大するのだろうか。「1頭あたりの配合飼料の量を増やしましょう」などとは口が裂けても言えないだろう。牛の頭数を増やすのだろうか。牛を減らすための補助金を1頭15万円も出していたのはつい2年前のことだ。
今まで自分で飼料を作る酪農家は大変な苦労をしてきた。だがその苦労が適正に評価されたことはない。輸入飼料のみで搾られた牛乳と単価は変わらないからだ。もちろん穀類を国内で作るのはまだまだ技術的にも難しい。しかし国内初の濃厚飼料を作る試みも始まっているし、デントコーン(青刈りトウモロコシ)サイレージなど濃厚飼料の減量にもつながる飼料作物の生産も各地で行われている。
国がやるべきことは、飼料や農産物を貿易交渉のカードにするのではなく、今まで国内で飼料作りを行ってきた農業者の再評価だ。そうでなければ飼料作りをしている農業者は作る意欲を失い、飼料自給率の更なる低下につながり、引いては食料自給率の低下にもつながる。輸入飼料を増やすことを国として選択することは間違いだ。


 新聞「農民」
新聞「農民」