参議院選挙は農政転換のチャンス 農民の要求実現できる政府を 要求運動、組織づくりと結んで全力をあげよう(2025年06月16日 第1654号)
農民連は6月6日、都内で全国代表者会議を開き、会場・オンライン合わせて39都道府県から100人が参加しました。参加者は、要求運動と組織づくりを前進させ参議院選挙で農政を変える決意を固め合いました。
たたかいの共同広げてきた運動

各地の経験を交流しました
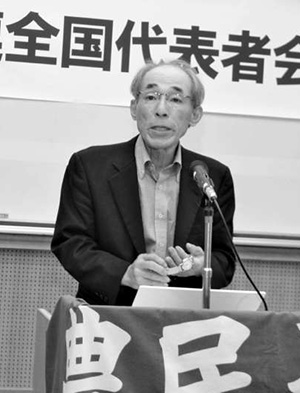
報告する長谷川会長
長谷川敏郎会長が開会あいさつと情勢報告を行い、政府備蓄米の放出で、テレビで「小泉劇場」が垂れ流されるもと、「米不足や価格の高騰は政府のたたき売りでは解決しない。いま求められているのは米の増産と生産者支援への本気の転換であり、今こそ農民連の出番。食と農の危機打開、米政策の抜本的な転換のために、広く国民的な世論づくりを急ぐ必要がある」と全国での奮起を呼びかけました。
2021年の米価大暴落のもとでの「3・19緊急集会」、9月24日の「中央行動」など米危機打開の行動、22~23年の酪農・畜産危機打開のたたかい、24年の「食料・農業・農村基本法」改定をめぐるたたかいで野党と国民との共同を広げてきた経緯を振り返りました。
過剰でも不足でも、米問題の解決の道を絶えず農民・国民に提起してきた農民連への共感が広がっており、それは全国の仲間が「農民連行動綱領」に団結し、「食と農の危機打開」に向けて、全国でたたかいを繰り広げてきたからだと指摘。トランプ関税問題でも5月16日にいち早く官邸前緊急抗議行動を呼びかけ、テレビでも報道されるなど、国民との共同の展望は広がっていると強調。「この確信に立って、無数の学習会や行動を広げ、会員と新聞『農民』を増やす絶好のチャンス」だと訴えました。
参院選で自公を過半数割れに
藤原麻子事務局長が常任委員会からの報告を行いました。
7月3日公示、20日投開票が予想される参議院選挙で、農民連が掲げる要求と農政の実現をめざし、自公の議席を減らして過半数割れに追い込み、要求の一致する勢力の議席増を勝ち取るために奮闘することを提起。(1)「農民」号外を広く届けて世論を変え、学習・対話を広げる、(2)参院選で多数の農家や有権者と対話して結びつきを強め、農民連への加入と新聞読者拡大を相乗的に前進させる―ことを訴え、参議院選挙を結節点にした米・農業を守るたたかいの方向を呼びかけました。
参議院選挙をたたかううえで、6月11日に消費者、流通業者、生産者が共同して米政策の転換と、トランプ関税に屈して米・農産物を差し出すことに反対する緊急農水省行動を提起。これを皮切りに全国で、学習会、集い、語る会など多様な集まりを全国無数に開き、「農民」号外を活用した学習会や宣伝・対話行動に取り組むことを訴えました。
消費税減税・インボイス廃止、戦後80年の平和、憲法を守る取り組みを呼びかけるとともに、たたかう農民連の姿に市民の中で共感が広がっているもとで、「農民連行動綱領の立場で運動に立ち上がろう」と訴えました。
さらに政府が増産に舵(かじ)を切って生産者支援に踏み出すためにも、自治体や農業団体、農家をあげた増産の推進が求められ、「ものを作ってこそ農民」の精神で地域から支えあって増産の先頭に立つことを提案しました。
年間を通した組織づくりを
藤原事務局長は、第26回定期大会以降、組織の後退に歯止めがかかっていないことを訴え、全国代表者会議から8月末までを「仲間づくり集中期間」として全力をあげることを提案。全国的に会員と読者の昨年11月現勢を突破するために全国で500人の拡大を目標に、会員で一県連あたり10人、読者10人以上の目標をたてて全国が一丸となって奮闘することを呼びかけました。
そのためにも参議院選挙勝利の取り組みと結んで宣伝・対話、学習会や集いを開き、要求を語って有権者が政党を選択する判断材料を提供し、会員と読者拡大につなげること、選挙だからこそ要求運動を前進させ、新規就農支援、青年部活動を重点に位置づけることを訴えました。
農民連ふるさとネットワークの湯川喜朗事務局長が米問題で特別報告。政府の減産押し付けが起こした米不足と価格高騰の本質を告発し、「需要に応じた生産」の誤りを隠すための備蓄米放出、備蓄制度破壊と外米依存の市場づくりが強行されていることを批判。「米をめぐる状況を正しく広げるため、学習を強化し、生産・流通・消費の各段階での連携で、政策転換を迫り、政治を変える国民運動を発展させよう」と呼びかけました。
各地の経験を交流し深め合う
討論では、20人が発言。各地で学習会、集いなど多様な集まりを開く課題では、多くの発言がありました。新潟県の鈴木亮事務局長は、毎週のように学習会で話す機会があり、米と農業を守るための独自のチラシを作製しています。北海道の富沢修一書記長も学習会で農業情勢を話し、「現場の農家の話を聞くのは初めて」などの声が寄せられるなど、広く農業情勢を伝える重要性を強調しました。
福岡県の藤嶋嘉子事務局長は、県内各地での学習会を通じて11部の新聞を拡大したことを報告。千葉県連の谷川聡子事務局長は、学習会参加者の疑問に答えながら、「新聞を購読することが私たちと一緒に運動すること」だと訴えて拡大しています。埼玉県連の立石昌義会長は、食健連の駅頭宣伝で「農民」号外を活用し、他団体の集会などでも配布する決意を表明しました。
多様な要求での運動を前進させ、地域で支え合って生産や運動に取り組む課題では、岩手県の岡田現三事務局長が、要求アンケートに取り組み、一緒に地域を守る運動への参加を呼びかけ、百姓一揆を計画していることを報告。和歌山県の土井康弘会長もアンケート活動で対話を進め、行政への要請を行っていると述べました。
昨年の石川・能登半島の地震と水害の問題では、石川県の宮岸美則会長、富山県の水越久男副会長が、復興が一向に進まない被災地で、住み続けられる地域にするにはどうしたらよいのかを考えながら、実態調査に足を運び、被災者を激励しつつ仲間を増やしている実践を報告しました。
奈良県の竹島茂直副会長は、県連の若い人たちを中心に仲間づくりの土台を作り、多様な要求で楽しく持続的に前進している成果を語りました。
最後に、笹渡義夫副会長がまとめと閉会あいさつ。「食と農の危機打開のために奮闘している経験が豊かに出された。今まさに農民連の出番。自民党農政を変えるためにも、参加者のみなさんが知恵を出し合い、力を合わせて前進しよう」と呼びかけました。
国会情勢報告とあいさつを日本共産党の紙智子参院議員が行いました。


 新聞「農民」
新聞「農民」