佐賀・福井・石川の県母親大会で長谷川会長が講演・報告 “報告を力に運動広げたい”(2024年07月29日 第1611号)
農民連の長谷川敏郎会長はこの間、佐賀、福井、石川の各県で開催された母親大会で、基調講演、報告を行っています。
大会後も各県で、長谷川会長の報告を力に学習と運動を広げようという動きが生まれています。
パンフレットの普及や新聞「農民」拡大の成果もあげています。各県の取り組みを紹介します。
農業・農政知るために「農民」購読を訴える=佐 賀=
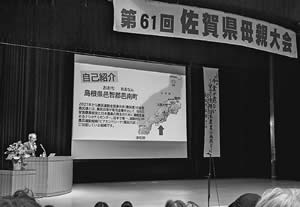
全体会で講演する長谷川会長
6月23日に第61回佐賀県母親大会が佐賀市で開催され、約250人が参加しました。長谷川会長が「いま、食が危ない!」というテーマで記念講演を行いました。
豊かと思われている現在の日本でも6人に1人が1日3食を食べられない「欠食児童」であることや日本の飢餓人口は2022年には3・2%(400万人超)にもなっていることを紹介。
農業の担い手が20年で240万人から136万人に減少し、うち約半数が70歳以上であることなどを紹介しながら日本の食や農業が直面している危機を告発しました。
長谷川会長は引き続き午後の分科会「豊かに育つ子どもの環境を考えよう」にパネリストとして参加。安心・安全な給食の実現にかかわって佐賀県では2023年度から給食用のパンに県産小麦が使用されていることを紹介しました。参加者からは「日本の農業があまりにもひどい状況にあることを知らなかった」「もっと農業のことを知りたいがどうすればいいのか」という声も聞かれました。
私は「いいものを買いたいというだけの消費者から、いいものを作る生産者を応援する消費者になってほしい。農業や農政の現実を知るために新聞『農民』を購読することが農業を応援することにもなる」と発言しました。
大会終了後に新聞購読の問い合わせが2件ありました。農業や食の実態を多くの人に知ってもらうためにもこうした機会を積極的に増やしていく取り組みが必要だと思いました。(佐賀県農民連 川﨑五一)
当日の資料印刷して新婦人各支部に配布=石 川=
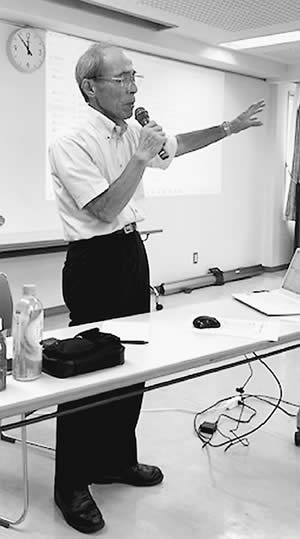
分科会で報告する長谷川会長
6月16日に金沢市で開催された石川県母親大会の農業問題分科会で、長谷川会長は「日本の食料問題と農業の未来」で約1時間の報告をしました。
「食料・農業・農村基本法」改定の国会での審議状況について話したほか、長谷川会長が自ら進めているアグロエコロジーの実践、牛飼いとたい肥作り、循環型米作り、里山の木材を使った薪ストーブ生活の話が大変分かりやすかったです。
アグロエコロジーは、世界の主流になっていること、学校給食をオーガニックにする取り組みも広がってきているが、もっと広げていく運動が必要だと強調しました。
新日本婦人の会石川県本部は、事前に『アグロエコロジー宣言(案)』パンフレットを役員で読み合わせして準備しました。長谷川会長の母親大会でのパワーポイントの資料を印刷して各支部に配布し、『アグロエコロジーパンフレット』を使った学習会も始まっています。
石川農民連も学習会に出向いて一緒に運動に取り組んでいきます。
長谷川会長の講演後、新聞「農民」の購読申し込みが3人の方からありました。(石川農民連 宮岸美則)
長谷川会長の講演はまさに 「目から鱗」=福 井=
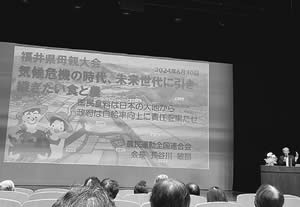
記念講演で報告する長谷川会長
6月30日に福井市東部の福井県生活学習館ユー・アイふくいで、第55回福井県母親大会が開催され、昨年を上回る約150人の参加者がありました。新日本婦人の会の高橋義枝事務局長はじめ実行委員会が事前準備に汗しました。
会場では、『アグロエコロジー宣言(案)』『新農業基本法の提言』のパンフレットを150部ずつ取り寄せ、それぞれ43部、26部を販売し、新聞「農民」も受け付け時に参加者の一人一人に手渡しました。
長谷川会長の「気候危機の時代、未来世代に引き継ぎたい食と農」と題した記念講演は参加者にとって、まさに目から鱗の内容でした。
以下、参加者からの感想の一部です。
「福井、日本の自給率(米、小麦、大豆など)の実態を知りました。現政権を変えないと日本人の健康・いのちは戦争の前に守れない。外国に学んで農政を変えないと!」
「豊かな土地が日本にあるのに、今の政府は輸入によって国民の食料を得ようとしている。農民連が掲げている『国民の食料は日本の大地から』の通り安全なものを安心して食べたいです。食品購入時は、国産で県産のもの、近隣のものを見て買っています」
(福井県農民連 加藤吉則)


 新聞「農民」
新聞「農民」