クロマグロの沿岸漁業漁獲枠の拡大を 求められる沿岸漁業優先への政策転換(2024年09月09日 第1616号)
国際会議で決まったクロマグロ漁獲量の増枠
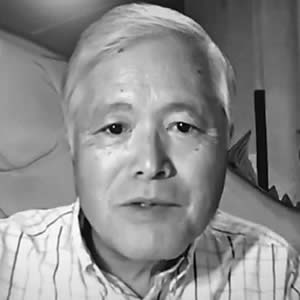
二平(にひら) 章(あきら)
全国沿岸漁民連事務局長、FFPJ(家族農林漁業プラットフォーム・ジャパン) 副代表
今年7月に国際漁業管理機構である中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)が北海道釧路市で開かれ、2025年からの太平洋クロマグロの漁獲枠を、大型魚(30キロ以上)は現行の1・5倍、小型魚(30キロ未満)は1・1倍にすることが合意されました。12月のWCPFC年次会合で承認されると、来年1月から実施されます。
ここで今、問題となっているのが国内での小規模沿岸漁業への漁獲量配分枠です。
太平洋クロマグロの漁獲量管理とは
太平洋クロマグロは、日本周辺で生まれ、3歳で30キロ、6歳で100キロ、10歳で200キロに成長、産卵開始は4歳、寿命は20歳以上です。北太平洋を広く東西に回遊し、主に日本、韓国、台湾、米国、メキシコなどが漁獲国です。太平洋クロマグロの親魚(しんぎょ=成熟した魚)の資源量は、1960年に約15万トンありましたが、クロマグロ幼魚の発生量変動や乱獲の影響で、2010年には約1万トンにまで低下してしまいました。
そこで、WCPFCは、資源回復をめざし、小型魚の漁獲可能量を、基準年(02~04年)の平均漁獲量8015トンの半分の4007トンにする規制強化を決定、大型魚は基準年の水準を維持する漁獲量管理をスタートさせました。
これを受け日本でも本格的なクロマグロの漁獲量管理が2018年から始まりました。沿岸漁民たちもクロマグロの国際的な漁獲量管理には賛成でしたが、ここで問題となったのは国内での大規模まき網漁業と小規模沿岸漁業との間の漁獲量配分でした。
水産庁の配分案は、小規模よりも大規模漁業(とくに大・中型まき網漁業)優先の内容でした。2万隻以上にのぼる沿岸釣り漁業と定置網漁業など沿岸漁業への配分量は、小型魚1317トン・大型魚733トンにとどまる一方、わずか数十隻の大中まき網漁業など大規模漁業へは小型魚1500トン・大型魚3063トンとしたのです。
反対の声を無視し強行したクロマグロ漁獲規制

クロマグロ
2018年6月に「この配分枠では生活ができない」とクロマグロを漁獲する全国の漁民が農林水産省前に集まり抗議集会を開催し、農林水産大臣に配分枠の見直しを行うよう強く申し入れました。
しかし、その後も国は、当初の沿岸漁業枠と大規模漁業枠との基本的な配分枠を変更することなく今日まで漁獲量規制を続けています。このため、この6年間、クロマグロを漁獲対象にする沿岸釣り漁業者らは漁獲配分枠がきわめて少なく、クロマグロが眼前の海に来遊しても漁獲することができず、漁民いじめの漁獲規制の罰則だけが強化されているのです。
さらに、沿岸漁業の主な漁獲対象であったスルメイカの大不漁もあり、今、沿岸漁民の経営は極めて困難な状況に追いやられています。このため沿岸漁民のなかには、すでに漁業をあきらめて離脱した者、新規参入をあきらめる若者たちが出てきているのです。
国連は小規模沿岸漁業を大切にせよと宣言
FAO(国連食糧農業機関)は、「責任ある漁業のための行動規範」(FAO・1995)や「持続可能な小規模漁業を保障するための任意自発的ガイドライン」(FAO・2018)などの国際的な政策文書を発表し、世界で9割以上を占める小規模沿岸漁業を守ることの重要性をうたっています。このためEU(欧州連合)諸国では、漁獲量管理にあたっては小規模沿岸漁業者に対して経営に配慮した漁獲枠の配分が保障されています。
これに対してわが国の国内配分は、大規模漁業優先で小規模沿岸漁業の漁獲枠が小さく、小規模漁業を大切にせよとした国連文書に反するものとなっているのです。
沿岸クロマグロの漁獲枠を大幅に拡大させよう
この6年間の沿岸漁民の多大な犠牲のもとで、2010年に約1万トンにまで低下したクロマグロの親魚資源量は、WCPFCが資源回復目標とした12・5万トンを達成期限より13年も早く突破し、22年には14・5万トンに達して今後も増加することが予想されています。
今、国は2025年1月からの新たな国内配分枠を決めるための検討に入っています。国内配分枠の検討にあたっては、これまで沿岸漁民を苦しめ諸悪の根源となってきた2018年の大規模漁業と小規模沿岸漁業の国内配分枠を、根本から見直させる必要があります。
国連の訴えに応え、日本でも小規模沿岸漁民が安心して生活できるよう、沿岸クロマグロの漁獲枠を大幅に拡大させることが重要課題となっているのです。


 新聞「農民」
新聞「農民」