第2回 全国オーガニック給食フォーラム 茨城・常陸大宮で開催 全国に広げよう有機農業 生産者、消費者、行政・農協も一体になって(2024年11月25日 第1627号)
オーガニック給食を全国に広げようと、第2回全国オーガニック給食フォーラムが11月8、9の両日、茨城県常陸大宮市で開かれ、8日のフォーラムは会場参加800人以上、オンライン参加400人以上が参加し、サテライト会場は51カ所で行われました。
給食を核にした自給圏つくろう

常陸大宮市の取り組みでは学校関係者、生産者らがスピーチしました
主催は、常陸大宮市オーガニック給食フォーラム実行委員会。実行委員長の鈴木定幸・常陸大宮市長があいさつし、「地方があるから都会での生活が成り立っているのであり、国は地方に光をあてる政策を行ってほしい。農薬使用量が世界2位の日本で、子どもたちの健康を守るためにも新しい農業、学校給食を広げることが私たちの使命だ」と述べました。
基調講演を2氏が行い、鈴木宣弘・東京大学大学院農学生命科学研究科特任教授が「給食が拓く子どもたちの未来~行政、協同組合の役割」と題して報告。戦後、アメリカの余剰農産物が日本に押し寄せ、アメリカに都合の良い食生活、学校給食が進められたことを批判。
「今、自国防衛のため、食料や化学肥料の原料の輸出を止める動きが広がっており、食料増産、備蓄で国民の命を守ることが重要。肥料も種子も海外に依存しないで、国内で循環できるようにしていくことが必要」だと強調しました。
さらに、改定「食料・農業・農村基本法」が、自給率向上を投げ捨て、農業に企業が参入しやすいようになっていることを告発。「稲作で手元に残るのは1万円で、時給10円では農家はやっていけない。都市と農村が融合した循環圏をつくり、学校給食での有機米買い取りで、農家もがんばれる、子どもたちは元気になる、こんなにいい循環はない。できる限り地域循環で、給食を核にした自給圏を一緒に作ろう」と訴えました。
企業参入許さずオーガニックを
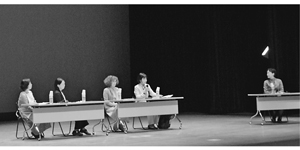
オーガニック給食には女性たちも活躍しています
「いのちの給食が世界を変える~私たち大人が手渡せるもの」のテーマで国際ジャーナリストの堤未果さんが講演。
堤さんは、アメリカ大統領選挙にふれ、モンサント社訴訟の原告側弁護士であるロバート・ケネディ・ジュニア氏がトランプ陣営につき、「まず子どもたちの食を変える」と企んでいると述べました。
アメリカ発の食は巨大企業で、世界中の子どもと学校を狙っているとし、アメリカの食生活の7割が遺伝子組み換えのトウモロコシから作られた人工甘味料などの超加工品だと指摘。日本では、大豆ミートが学校給食に使われ、原料は遺伝子組み換え大豆で、ブラジルの森林を伐採して作られ、大量の添加物が使われていると告発しました。
今年1月にスイス・ダボスで行われた世界経済フォーラムでは、(1)遺伝子組み換え(2)無人農業(3)肉、魚、乳製品は人工(4)昆虫食――の推進を提言し、大手企業が次々参入することを狙っていると指摘。
一方で、オーガニックが、地元の生産者の安全な農産物を使用することであることを強調。
ローカルフード法を次の臨時国会に再度提出する予定であることを報告し、「オーガニック給食を通して世界を変え、日本から未来を変えていこう」と呼びかけました。
有機農業の実践農協でも広がる
オーガニック給食を実現したJAからの報告では、JA東とくしま(徳島県)参与の西田聖さんが、田んぼは人工的湿地帯であり、環境保全の観点からラムサール条約の水田決議の重要性などについて話しました。
続いて、茨城県のJA常陸、秋山豊代表理事組合長が報告。農協と行政がタイアップして3年目を迎え、常陸大宮市の鈴木市長が公約として、学校給食の100パーセントオーガニック化を掲げたことから、じゃがいも、サツマイモ、かぼちゃ、にんじんの有機農業に取り組み、すべて成功したことを紹介。水稲も、NPO法人民間稲作研究所の指導を受け、学校給食に提供して余った米を有機米「ゆうき凛々(りんりん)」として販売しています。
常陸大宮市からは、市の学校給食オールスターズとして、小学校の教員、調理師、農家、JA職員、市職員から事例発表がありました。
有機農業推進に女性たちも活躍

ロビーに設置された有機農産物の展示
パネルディスカッションとして、「子どもたちを守り、地方を輝かせる環境時代の給食とは~各地で活躍する女性たちにきく~」のテーマで討論。司会をノンフィクション作家の島村菜津さんが務めました。
4氏がパネリストとして発言。農林水産省大臣官房審議官兼経営局の勝野美江さんは、徳島県副知事時代に「徳島県版みどりの食料システム戦略基本計画」を策定し、県が、人、環境、社会に配慮した持続可能な方法であるエシカル農業とエシカル消費の2つの考え方で進めていったことを報告しました。
オーガニック給食マップ事務局で前パルシステム生活協同組合連合会副理事長の野々山理恵子さんは、オーガニック給食マップは2021年に立ち上がったウェブサイトだと紹介し、以前生協の代表を務めていたことから、生協の目標は共生の社会をつくることだと述べました。コミュニティーの3・5%以上の人が参加していれば、社会を変えられることもあるという、3・5パーセントの法則を紹介しました。
石川県の白山環境給食まちづくり協議会代表の米山立子さんは、今年2月に発足したまちづくり協議会で、「自分たちでできることをできる範囲でやっていこうとしている」と話しました。
茨城県龍ケ崎市の横田農場、横田祥さんは、減農薬と有機農業を実践し、170ヘクタールで水稲をつくっています。「おこめLABO(ラボ)」で農業体験、料理教室を行い、食育絵本の読み聞かせに取り組み、「農業は楽しい」と伝えるアグリバトンプロジェクトでは当初3人で始めましたが、現在169人に広がっていると語りました。
最後に、次回(第3回)フォーラムが2年後に栃木県小山市で開催予定であることが発表され、小山市の浅野正富市長が閉会の言葉を述べました。
浅野市長は、「今年は有機米の作付けが20ヘクタールを超えるようになったが、小山市の場合、オーガニック給食をすべて有機米で対応しようとすると約60ヘクタールを耕作しなければならない。2年後、みなさんをお迎えするころには60ヘクタールを達成できるようにしたい」とあいさつしました。
2日目の9日は、現地研修会が行われ、有機野菜のほ場見学や有機農産物フェアが行われました。


 新聞「農民」
新聞「農民」