各地から明日をめざすたたかいが 農民連青年部が第33回総会を開催 農民連を大きくし、農業・農村を守る(2025年03月24日 第1643号)

報告する渡辺事務局長(右)
農民連青年部は3月8、9の両日、第33回総会を大阪市内で開催しました。山形・福島・群馬・東京・奈良・和歌山の6都府県から約20人が参加しました。
総会では、渡辺信嗣事務局長が報告。米不足や米価の高騰、畜産の窮地など日本の食と農をめぐる危機の根底に、食に対して無責任な政治があることを指摘し、「農業・農村を守るためには農民連を大きくすることが必要」と述べ、そのために青年部組織の確立・強化を進めること、世代間や青年の交流学習を強化する方針を提案しました。
討論では参加者から営農の現状や活動の報告がありました。
農民連の活動の大切さ実感する
福島・須賀川農民連の桑原翔太朗さんはハヤブサの会の立ち上げの経緯や、新規就農受け入れの取り組みを報告。「新規就農者への支援は自治体によってまちまちで、研修がメインとなる作物の栽培技術の習得で終わってしまい、農家として生活するのに必要な知識が身についていない場合も散見される。そうしたことが起きないように、自分たちの経験を伝えていきたい」と、若手農家が主体となっての営農計画のサポートなどを予定しています。
和歌山県海南市の小倉和也さんは、梅やモモ、桜などでクビアカツヤカミキリの被害が拡大している現状を報告。「ひどいところでは園地の半分以上に被害が出ていて、防除の方法もわからず、被害が出た木を伐採するしか方法がない。改植支援の拡充が必要です」と話しました。
奈良県農民連青年部長の原澤厚治さんからは今の農政について「政府は完全に見捨てている」と市場に丸投げの農政を批判し、「農民連に入って10アールでも自分で米を作ろうと呼びかけたい」と決意を語りました。
群馬県嬬恋村の酪農家、山村聡さんは「エサ代は生まれてこのかた下がったことがない。今は乳価120~125円(1キログラム当たり)のうちエサ代が108円程度を占め、さらに光熱費もかかって赤字になる。機械も値上がりしており、買いたくても買えない。エサ代、特に干し草への補助をしてほしい」と要望を述べました。
山形・庄内農民連の阿部佑一さんは「販売は直販と産直センター出荷だが、資材の購入だけでも農協に入って多方面から農政にアプローチできるようにしている。県農協青年部の会長として自民党議員などにも要請できるので、こうしたパイプも活用して少しでも農業を良くしたい」と話しました。
討論のまとめで、平間徹也部長は「農家の声を届ける農民連の活動の大切さをあらためて実感できる討論でした。ぜひ今年は青年部での農水省交渉を再開させたい」と述べ、全員一致で決議案を採択しました。
食品添加物の学習会を開催
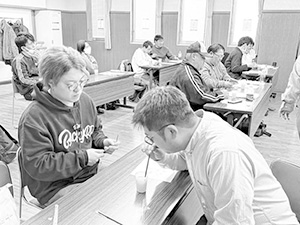
実験を通じて添加物の現状を体感
2日目はNPO法人食品安全グローバルネットワークの中村幹雄さんを講師に招き、「どうなっちゃうの? 日本の“食”~私たちにできること~」と題して食品添加物に関する学習会を開催しました。
中村さんはコレステロールや水素添加油の健康への影響など、これまで通説となっていることに誤りがあることを指摘。また国内で開発された紫芋が中国に持ち出され逆輸入されており、「色素もほぼ輸入に頼っているビタミンCも、国内で生産できる」と挑戦を呼びかけました。
また人工甘味料についても、「近年の研究で人工甘味料の長期摂取が肥満や糖尿病、がんのリスクを増加させることや環境中に残存し環境汚染を引き起こすことが分かってきた。人工甘味料の普及で北海道の製糖工場が一カ所閉鎖になり国内農業にも大きな影響のある問題だ」と述べました。
「国民の健康で文化的な生活を守るために、国産でまかなう農業をめざす。国から独立した評価機関を作り、過度な添加物の依存から抜け出す必要がある」と提起し、新たな需要喚起や農民連の強化、専門家との連携を呼びかけました。
学習会では人工ジュース作製やソーセージの発色剤の検出などのワークショップも開催し、参加者は夢中になって取り組んでいました。
無農薬での米・野菜作りを報告
また、和歌山県農民連の髙橋範行さんが無農薬での米・野菜作りについて報告。「慣行・有機の別なく、ものを作り続けることが大切。一緒にがんばっていきましょう」と呼びかけました。


 新聞「農民」
新聞「農民」