「農業のこれから」若い営農者ら語る 「だんだんCPPジャパン」 オンライン学習会(2025年07月28日 第1660号)
熟練農業者からの技術習得が急務
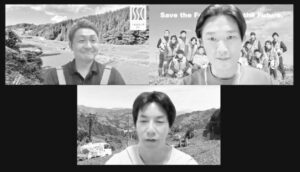
(左上から時計回りに)タクロンさん、中森さん、村上さん
6月26日、日本の米情勢について生産現場の声や輸入米の視点から学ぼうというオンライン学習会が開かれました。主催はNPO法人「こどもと農がつながる給食だんだん」(CPPジャパン)で、後援は日販連(日本販売農業協同団体連合会)。
「だんだん」は子どもたちの成長のために学校給食について地域と一緒に考え、より豊かなものにしよう、という活動を行っています。
講師は3人で、青森県黒石市の農業法人「アグリーンハート」代表取締役の佐藤拓郎(タクロン)さん、埼玉県加須市の農業法人「中森農産」代表取締役の中森剛志さん、農民連の新聞「農民」編集部の村上結さん。
価値観の共有が農業を強じんに
約80ヘクタールの経営面積のうち60ヘクタールを有機で営むアグリーンハート。タクロンさんは市の観光大使であり、元テレビリポーターで、県や国の農業政策の委員を務めています。「米の適正価格はいくらか?」という問いについて、「ミネラルウオーター500ミリリットルが1本120円とすると、60リットル(60キログラム)で1万4400円になる。これは2023年の米農家の60キログラム販売価格とほぼ同じ。これが安いのか、高いのか。適正価格は価値観の共有だと思う」と提起。
経済が発展し、生産地と消費地の分断が起き、今は「誰が生産したのか分からない消費」と「誰が食べるか分からない生産」が当たり前になっている中で、「『目に見える範囲内での経済圏をつくる』ことが今後の農業をより強じんにする」と語るタクロンさん。「一緒に働く仲間、理念に共感して関係を構築してくれる人たち(企業や取引先)やお客さんと『価値観』を共有していくこと。これからの農業法人にはこれが求められる。有機米は、互いが目指す未来の実現のための手段の1つ」と力強く語りました。
地方創生が食料安全保障を確立
埼玉、栃木、島根、山口で計330ヘクタールの水田を管理し、後継者のいない農業法人を全国で積極的に事業継承している中森農産。経営方針は「日本の食料安全保障の確立」と話す中森さんは、「日本の農業でいま一番必要なのは“農業をやる人・農地を守る人”を増やすこと」と力説します。
「地方において全国的に再現性がある経営資源が農業。地方で農業によってどれだけ付加価値を生み出せるのか。それに挑戦することが真の地方創生であり、人々の食を守ることになる」という信念を語る中森さん。同時に、「それは大規模農家だけが生き残るという未来ではないし、いま私たちが急いで取り組むべきは地方の熟練農業者の方々と協力すること」だと強調。各地の熟練農業者がどれだけすごいノウハウを持ち、どれだけ農村の維持に貢献しているのかを理解し、その技術を習得する必要性を述べ、「これが事業継承を展開する意義であり、そのためのイノベーション(技術革新)の導入も必須」だと語りました。
農民連の村上さんは、農民連が当初から縮小・廃止を訴えてきたミニマム・アクセス(MA)米の経過を紹介し、「MA米の輸入は義務ではない」ことを強調。小泉進次郎農相がやってきた政策や対応について、「ひたすら米の店頭価格を下げるための措置であり、米不足解消と日本の農業を守るための手立てにはなってない」と語り、「令和の米騒動を『主食用米の継続的な輸入拡大』で決着させてはいけない」と訴えました。


 新聞「農民」
新聞「農民」